「普通じゃない」自分
を責める私
友だちと山や川で遊んでいるとき
自分らしくいられる
私は幼い頃から、自然が大好きな子だった。
幼稚園の裏山や家の近所の山や川で友達と遊ぶ時間が大好きで、日が暮れるまでずっとずっと遊んでいた。
そんな私はいつ頃からか、誰が決めたか分からない「普通」と自分を比較して、その枠からはみ出てる自分は「普通じゃない」「おかしいんだ」と思うようになっていた。
みんな当たり前に元気よく発表してるのに、自分は人前に立って発表しようとするだけで涙が止まらなくなってしまう。 いま人前で話すことを仕事にできてるのが不思議なぐらい人前がダメな子で、うまく発表できなくて、発表の場面の度にみんなの前で泣いて、恥ずかしかった。
女の子だったら自然と男の子を好きになるはずなのに、自分は気づくと目で女の子を追いかけて、心惹かれてしまう。自分でも理由は分からないけど、私は幼い頃から女の子にときめいていた。
なんで自分はみんなと違うんだろう。
なんで自分は周りの子と同じようにできないんだろう。
私は自分と人との違いを感じるとすぐ不安になっていたが、友達と山や川で遊んでいるとそんなことなんか忘れられて、のびのびと自分らしくいられた。
「普通」に当てはまらない自分がいけない
小学校の高学年になると、自分の知らない間に友達づきあいのルールが変わっていて、女の子のめんどくさいグループ同士のいざこざに巻き込まれた。
「何でさーちゃんは色んなグループの子と遊ぶの?」「普通、1つのグループに所属するもんでしょ。」「どっちのグループに入るか決めて。」
自分は今まで通り、遊びたいときに遊びたい人と遊びたい。
ついこないだまで、みんなだってそうやって遊んでいたのに、急にそんなことを言われて、私は混乱した。
「なんでそんなにグループにこだわるの?」「変なの、そんなの関係ないじゃん。みんなも遊びたい人と遊んだらいいじゃん」そう伝えたいのに、うまく言葉にできない。
女の子たちが「なんで?」「どうするの?」と問い詰めてきて動揺したし、自分だけがそう思ってるのかと思うとすごく心細かった。
どうしたらいいのか分からなかった私は、あいまいな返事をした結果、女の子たちからいじめを受けた。
彼女たちは自分を徹底的に仲間外れにするようになった。
こないだまで仲良く遊んでいた子たちが、突然自分のことを無視して、ひそひそ陰口を言ったり指差してきたりする。 1人で掃除を押し付けられる、そんな自分の姿を見て嘲笑ってくる。周りで遠巻きに見てる子たちも、巻き込まれたくなくて何もしてこない。 誰も助けてくれない。
彼女たちの思う「普通」に当てはまらない自分がいけないんだ。
「普通じゃない自分」のことを責める私がいた。

友だちが
一瞬で敵になる経験
日に日にすり減っていく心
中学校で入ったバスケ部でも陰湿ないじめがあった。
顧問にはばれないように、ターゲットを1人に絞っていじめる。同級生たちが1人、また1人と辞めていく。
私はとにかく大好きなバスケットボールがしたい、もっと上手になりたいと純粋に思っていた。だからもう、めんどうなことに関わりたくない。そんな風に、我関せずでバスケに没頭していたら気づいたときには、自分がいじめのターゲットになっていた。
部活中、永遠と続く無視。ボールを回してもらえない。私の言動、プレーを見ては「おかしいんじゃない?」とひそひそ嘲笑ってくる。昨日までボールをパスしてくれた子たちが、一瞬で敵になってしまったのがショックだった。
こんな理由で大好きなバスケットボールを諦めたくない。でも、私の心は日に日にすり減っていった。「なんで自分はここにいるんだろう」「何のために自分はここにいるだろう」プツっと糸が切れたように、部活を辞めた。

自分の「好き」を諦めてしまった
「今までごめんね」「お願い、戻ってきて」部員が減って部活が続けられなくなった途端、180度態度を変えて泣いてお願いしてくるチームメイト。いまさら、そんな言葉いらないよ。もう、あなたたちとバスケしたくないよ。とにかく1人になりたくて、みんなから離れたくて、違う部活に入った。
今思えば、これが彼女たちへの私なりの復讐だったのかもしれない。チームメイトをいじめて排除していった結果、自分たちの首を絞めることになったのだから。
適当に「お前は変だ」「普通じゃない」と理由をつけて、寄ってたかって、痛めつけて、面白がって。
飽きたり都合が悪くなったら、コロッと態度を変えて。
人のことなんだと思ってるんだ。バカにしてる。純粋な怒りだった。
でも、それ以上に悔しかった。
自分が本当に大好きでやりたいと思ったものを諦めてしまった。自分の大事な「好き」を守れなかった自分に腹が立った。自分が情けなかった。初めて自分の心の大事な部分を折られた経験だった。

中学生の頃
「いつも笑顔で面白い子」
の仮面
苦しいとき、味方になってほしいときほど、
誰も助けてくれない
この2つのいじめを経験した私は、友達や仲間と思った人でも何かの拍子に「普通」を押しつけてきて、簡単に「敵」になってしまうことを学んだ。
「普通じゃない私」でいると、「普通のみんな」から仲間外れにされる。そんなのもう2度と味わいたくない。そして、苦しいときこそ、味方になってほしいときこそ、誰も手を差し伸べない。自分が傷つくのが嫌だから、見て見ぬふりする。私だってそうだ。
自分の身は自分で守らないと。
そう思った私は、自分の「普通じゃない部分」がばれないように、自分の本音を隠して何でもないふりをし続けた。
悩みも、葛藤も、全て抑圧して、受け入れてもらいやすい「いつも笑顔で面白い子」の仮面をつけて自分を隠した。「普通のみんな」の中にさえいられれば、いじめられることはないだろう。自分の大事な部分を傷つけられる心配もないだろう。
実際そうすることで、高校時代は友達がたくさんできたし、にこにこして面白いことを言う自分の周りにはいつも人がいた。「普通じゃない私」でも「普通のみんな」と一緒にいることができた。自分の望んだ平和な学校生活のはずだった。

一瞬たりとも隙を見せられない
でも、私の心の中はいつも不安でいっぱいだった。どれだけ友達に囲まれてても、大爆笑していても、私はひとりぼっちだった。本当に心許せる友達はいなかった。笑顔の下で、私の心はいつも警戒態勢をとり、周りをじっとうかがっていた。
また、いつ仲間外れにされるか分からない。何かの拍子に「お前はおかしい」「仲間じゃない」と言われるかもしれない。 LGBTQ、セクシュアルマイノリティという言葉すらまだ世に知られていなかった当時、女の子に心惹かれる私のセクシュアリティは普通じゃないものだった。
私は誰よりも「自分はおかしい」「普通じゃない」と知っていた。
「さーちゃんは誰が好きなの?」「どんな人がタイプなの?」友達の輪の中で恋愛の話が出る度に、心臓がバクバクした。一瞬たりとも隙を見せられなかった。
「普通」に見せないと、また仲間外れにされてしまう。
笑顔の仮面をつけて友達と一緒にいても、安心感やつながりは感じられなかった。

ロクデナシの兄と
うまく隠せてしまう自分
ひそかに歌っていた歌
THE BLUE HEARTS / ロクデナシ 役立たずと罵られて 最低と人に言われて 要領よく演技できず 愛想笑いもできない 死んじまえと罵られて このバカと人に言われて うまい具合に世の中と やっていくことも出来ない 全てのボクのような ロクデナシのために この星はグルグルと回る 劣等生でじゅうぶんだ はみだし者でかまわない ----------------
家で1人、ひそかに歌っていた歌。自分のセクシュアリティの特異さに気づきだした思春期の頃、この歌に励まされていた。
この歌は私の兄のことも歌ってくれていた。私の4つ上の兄には精神疾患・発達障害がある。私が低学年の頃からその性質は徐々に表出しはじめた。
周りに迷惑をかけまくる兄が、うらやましかった
兄に私の家族は振り回されっぱなしだった。家族でさえ兄の行動が理解できず、我が家はトラブルと混乱の渦で、常に緊張状態。兄はトラブルを起こしては入退院をずっと繰り返し、ご近所さんや警察にもたくさん迷惑をかけた。
そんな生活に家族全員が疲弊していた。
私は異質な兄と一緒にいるのを友達に見られたくなかった。明らかに友達の兄弟と違う兄が、我が家が、恥ずかしかった。と同時に、私はひそかに兄のことを「ロクデナシ」仲間だと思っていた。
セクシュアルマイノリティに精神疾患・発達障害だなんて、どう考えても、私たちは世間の「普通」からのはみだし者だった。
私は、自分の「普通じゃない部分」をありのままに表現する兄を間近で見続けて、ものすごく怖かった。
でも、それと同時に劣等生でじゅうぶんだ、はみだし者でかまわない。そう表現できてしまう兄がうらやましかった。
周囲に迷惑をかけまくる兄がうらやましかった。正真正銘のロクデナシの兄がうらやましかった。
自分も本当はそうなのに、そうしたいのに、うまく隠せてしまう、周りに合わせられる自分が嫌だった。
大好きな兄を裏切っているようだった。
両親は私のことを
全然分かってくれない
兄ちゃんをいじめるな!
大人たちは兄を「普通」に矯正しようとしたが、兄はずっとそれに抵抗し続けた。
兄が抵抗すればするほど矯正する力も強まり、トラブルが増え、
対立と混乱が日常になった。私はそれが怖かった。
兄が入院して、突然家からいなくなっても誰も何も言わない。
兄がいなくなったのに、当たり前に日常生活が続いていくことも、当時の私には怖いことだった。
なぜ兄がいなくなったのか、幼い私はよく分からないまま、これは触れてはいけないことなんだと思った。
私も兄のようにありのままの自分を表現し続けると差別され、攻撃され、
突然家族から引き離されて、「いけないもの扱い」されてしまうのかもしれない。
怖い、嫌だ。
でも、本当は、
「私も兄ちゃんと一緒でロクデナシなんだ!」
「兄ちゃんは兄ちゃんのままでいいじゃないか!」
「兄ちゃんをいじめるな!!」
そう叫びたかった。でも、怖くて叫べなかった。その時の私には声をあげる勇気はなかったし、幼い私の力では兄を守ることはできなかった。家族が兄のことで苦しむ姿を見るのも辛かった。
差別や無理解のせいで、これ以上、大事な人たちが傷ついてほしくない。みんな仲間で同じなんだって分かってほしい。そんな風に思っても、何もできなかった。
私は「力のない自分がいけないんだ」と思い、自分のことを責めた。
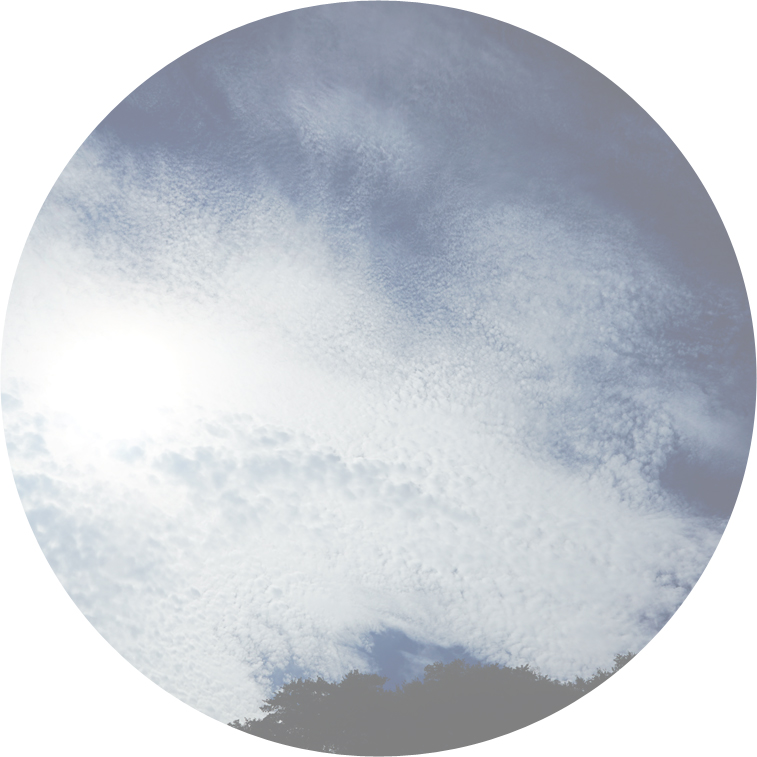
両親を兄に譲った、わたしは大丈夫
自分が弱くて幼いからいけないんだ。はやく大人になりたい。力が欲しい。そう願っていた頃。あれは確か小学校中学年ぐらいだったと思う。
ある日、躁状態の兄が家の屋根裏部屋から屋根に登り、大騒ぎしていた。落ちたら骨折は必須、打ち所が悪ければ死んでしまう高さ。両親は兄を降ろそうと必死に声をかける。私は、それを部屋の外から見ていた。
ひとしきり両親と兄の攻防が終わり、兄が屋根から降りてきた。
「いいかげんにしろ!本気で心配しとんじゃけ!!」
「もう、こんなこと2度とするな!!」
と両親は怒鳴り、大泣きしながら兄を抱きしめたのだ。
私は、はじめて両親が本気で泣いている姿を見た。
そして、3人で抱き合っている姿を見て、自分もあの輪の中に入りたいと思った。
でも、瞬時に「それはしちゃダメだ」と思い、部屋の外からずっと3人を見ていた。
多分、あの瞬間から、私は両親を自ら兄に譲った。本当に手がかかるロクデナシの兄には、両親が必要だ。
私は大丈夫。そう自分に言い聞かせた。
本当は傷つき、怒っていた
でも、本当は怖かった。
自分は両親にあんな風に抱きしめてもらえるのか。本気で心配して泣いてもらえるのか。
いま駆け寄っても私なんか見向きもされないんじゃないか。気づかれないんじゃないか。迷惑で邪魔なんじゃないか。
両親から拒絶されることが、家族の輪の中に入れてもらえないことが、私は何よりも怖かった。
そこから私は、両親に精神的に頼ることをやめた。
両親の愛情は、兄に注げばいい。私は要らない、私はひとりで大丈夫。
まだまだ甘えたい時期に、私ははやく大人になろうとした。
悩み事は言わないし、聞かれないようにする。いじめられたことも全く言わず、いつでもニコニコして楽しく学校で過ごせているように見せて、大丈夫なふりをして過ごしていた。
大きくなってからも、進路は全く相談せず、全部自分で決めた。
私は、聞き分けのいい、わがまま一つ言わない、いい子になりすました。そうすれば、両親の力になれるし、自分も傷つかなくてすむと思った。
「さーちゃんは、本当にいい子だね。」「いつもありがとう。」
両親にそう言われる度に、私は嬉しそうに振る舞ったが、本当は傷つき怒っていた。本当はそうじゃない。私は全然いい子なんかじゃない。両親は私のこと全然分かってくれない。そう思っていた。

小学生の頃